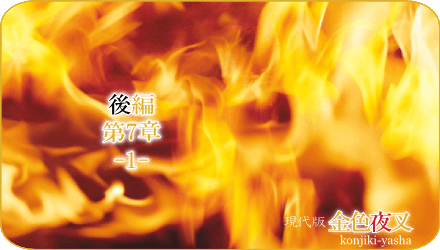最後の晩餐
最後の晩餐
我が子の仇、直行の首を獲ろうと毎夕訪ねて来る狂女。それは既に八日に及んでいた。直行らは鬱陶しいとは思いながらも、追い返し駆逐するほどのことでもないし、それに門前に居るからと言って騒ぎを起こすわけでもなかったので、とにもかくにもひたすら放置を決め込んでいた。
直行が述べていたように何だかんだで特別な害を及ぼさない以上は、野良犬が寝ていると思うしかなかったのだ。
それにしてもブラウンのコートを羽織った人物がたそがれ時の冷え冷えとする門前にうずくまって、白髪交じりの髪を掻き乱し、妖星の光にも似た両眼でギロリと睨み反らしている光景ったら。笑うかと思えば泣きはじめ、泣くかと思えば怒り、自身の胸中を表現したかのような黒く濁った夕暮の空に向かって、その悲しみと恨みを訴える有様ときたら。その正体は、生臭い油紙を捻っては人の首を斬り落とそうとしている狂女なのだ!
たとえ今現在において何の危害をも加えない存在だったとしても、いつかはこの家に祟りをなすべく黒い望みを沸々と抱いているに違いない。
人の執着の一念は水ですら火に変えてしまう。山だって海にしてしまう。鉄をつんざき、巨岩を砕くことだってあろう。まして家を根絶やしにし、人を皆殺しにすることなどは、塵を吹き払うよりも容易いはずだ。なんておそろしい。何事もなければ良いのだがと、お峯は独り言い知れない心の痛みを覚えていた。
直道は雅之の私文書偽造に関して、それが自らの手による策略の罠だったとは決してお峯に明かさなかった。それゆえに悪いのはあくまでも狂女であって、当方に恨みを受ける筋合いなどあるはずもないとお峯は信じていた。同様に自ずからこのような事件が起きる理由も、家業ゆえの宿命であり、金貸しにだって貸し倒れで大損することもあるのだから、相手を倒し倒される商売の勝ち負けの慣習は、貸し手借り手双方お互い様ではないかとも思っていた。
このように彼女の強い思い込みもあって、この老女の狂った原因がまさか我が夫の仕業だったとは全く考えなかったのである。
とはいえ子を思う人の親の切ない心情を鑑みれば、老女の本気度合いも推し測られるというもの。筋違いの逆恨みで災難に遇うことだってあるのだからと、彼女の心中には言い知れぬ恐怖が募ってゆく。
毎日毎日狂女が欠かさず通って来るのは、陰ながら我々の命を絶とうと謀っているため――しばらくの間、門前でじっと動かずにいるのは、妄執の念力を籠めて我々を呪うため――こんな妄想をしてしまうほどに、夕暮れ時のお峯は譬えようもなく悩まされた。
ならば狂女が門前に居座る間は、大御明尊の御前に着座し、しきりに祝詞を唱えるしか彼女に残された手段は存在しなかった。その間ですら心に僅かにでも緩みがあれば、煌々と輝くロウソクの影がどんどん大きく暗くなり、天尊の姿もおぼろげに消え失せてしまうかのように見えるのだ。ありがたい本尊の恵みも加護も切れ果ててしまうのではないかと、彼女は一心不乱に念を込め、煙を立てて、汗まみれになりながら、神にすがるのだった。
槍が降ろうが狂女は絶対来る。そう恐れ戦きながら九日目を迎え、例刻となった。しかしどうしたものか、狂女の姿はなかった。
鋭く冴え渡るこの日の寒気は、鍼で肌に霜を植え付けたかのようで、外は激しい風が怒号を奏でていた。風は木々を鳴らし、家屋を震わせ、砂を撒き上げ、小石を飛ばし、空は曇っているわけでもないのに、吹き上げられる埃に覆われて暗く乱れていた。日射しも黄色く濁り、ことに物恐ろしい夕暮れの気配を醸し出していたのである。
鰐淵の邸宅の門灯は風のせいでガラスが割れており、灯りも消えてしまっていた。一方、屋内は常よりも煌々と明るくダイニングテーブルを照らし、卓上コンロに掛けている鍋はぐつぐつと煮え、晩酌は早くもお代わりを飲む頃合いにまでなっていた。未だ狂女は来ない。
お峯は半ば警戒しつつも、幾分の安堵を享受する風情になっていた。
「頭がおかしいあの女もこの強風には敵わないみたいですね。いつもならとっくに来ているはずなのに、来ないんですから、今夜はもう来ないわね。いくらなんでもこの風じゃ、吹き飛ばされてしまうわ。ああ、ほんと天尊様のご利益さまさまだわ」
直行が猪口に酒を注いだ。
「ご相伴しちゃおうかしら。何はなくとも、こんな清々しい気分のときにいただくお酒は美味しいものね。あら、いやだ、そう続けて何杯も飲めないわ――まあ、あなた、あらまあ、もう七時を回ったのね。それならましてや今晩は来ないはずだわ。
じゃあ戸締りをしてしまいましょ。ほんと今晩のような気がせいせいする、心底嬉しいことはありませんよ。あの頭のおかしな女のおかげで、どれだけ寿命が縮まったことか。もうこれっきり来なくなるように、天尊様にお願いしなくちゃ。
はい、いただくわ。お酒も美味しい。なあに、あの婆さんがただ怖いってわけじゃないのよ。そりゃ気味が悪いのは気味が悪いですけれどね。怖いって言うよりも、気味が悪いって言うよりも、なんとなく背筋が凍るのよ。あれが来ると、ぞっと寒気がして身体がすくんでしまうのですからね。単に怖いって言うのとは違うの。
それが何だか、こう憑依されるような気がして。ほら、あれよ。よく夢で恐ろしいヤツなんかに追いかけられたときにね、逃げるに逃げられず、声を上げたくてもそれもできず、どうなるのやらと思う事があるでしょう? まさにあんな感じなのよ。ああ、もうこんな話はやめましょ。私、少し酔ったみたいだわ」

銚子を替えてお代わりを使用人が持って入って来た。
「あら、金さん。今晩はあのおかしな女、来ないわねえ」
「結構なことですね」
「あとでお菓子をあげるわ。あなた、金さんはね、あのおかしな女と最近懇意になってしまいましてね。アレの相手をさせるのは、すっかり金さんにお任せなのですよ」
「あら、イヤなご冗談をおっしゃって」
吹き渡っては吹き去って行く風は、大波が押し寄せては返すように絶え間なく轟いていた。その激しさは家の柱をギシギシと鳴り揺るがし、物を打ち倒すひしめきや、引きちぎる音、へし折る響きなどがここかしこに聞こえていた。ただじっとしているだけでも肝が冷える思いがする強風である。
暖房はフルパワーで稼働させ、加湿器からは湯気がしきりに立ち昇るけれども、それでも壁づたいに沁みて来る冷気は身震いするほどで、あたかも鉄板を背に負ったかのような心地。これでは呑んでも呑んでも、全然酔う気がしないではないか。直行は何合も銚子を空け、お峯までも祝いの気分からか飲み過ぎて、顔を真っ赤にしながら更にニスでも塗ったかのようなテカリ具合になってしまっていた。
結局、狂女は来なかった。嬉しくて喜び酔ったお峯も、単純に酒に酔った直行も、褒美をもらった使用人も、十時過ぎあたりには皆寝静まってしまった。
風はなおも激しく吹き荒れ、高い梢は箒で掃いたかのようにたわみ、まばらに空に散る星は、まるで風に吹き飛ばされて数を減らしたかのように見える。ますます寒さは厳しくなり、わずかに残った生気までも吸い尽くして、ただでさえ陰鬱な夜の色は殊に暗く凄まじくなっていった。
この漆黒の闇を劈(つんざ)いて、突如、鰐淵の邸宅の裏口あたりから一筋の光が立ち揚がった。