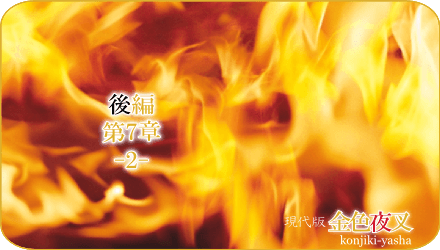業火
業火
火は足元近くの低い場所で上がり始め、物に遮られていたため、火なのか何なのか誰に気付かれることもなく燻ぶりだした。けれども、その迸(ほとばし)りが赤く煙れる中に見える母屋と物置の影は、おぼろげに現れた刹那にも瞬く間に消え失せてしまう。強風で火が消えてしまったのだろう。
しばしの時間が経った。同じような火影が、またメラメラと上がりだした。しかし早々に影は薄くなって今度も燃え広がらず、かといって消えもせず、しばらく仄かに燻ぶり続ける。
風が止んだ。機が来た。この絶好の隙を狙ったかのように、燻ぶった火は物置の戸を伝い、ここに来て激しく燃え上がりはじめた。炎が四方を照らす。塀の際に沿って人の形が動いているようにも見えるが、まだ暗くて定かではない。
瞬く間に火の手は縦横に蔓延りながら、物置の中にまで乱入した。噴き出る黒煙の渦は崩れ畳みかけるように外縁を包みこみ、奥に見える母屋も何もかもうず高い暗澹の底に没した。闇は炎に破られ、炎は煙に揉みたてられ、煙は更に風に砕かれつつ、激しいまでに勢いよく噴き出している。
行き場を失って狭所でみなぎり、変幻自在に文様を描いては掻き乱れる炎だったが、何かが弾けるような爆音とともに、天をも焦がすかのような猛火が発生し、巻き上がった。
猛火は定かではなかったあの人の形なるものの姿をも、明々と照らしだす。そこには毎夕欠かさずやって来ていたあの狂女が佇んでいた。
踊り狂う炎の下で泰然と立ち、顔がただれるかと見紛うばかりに照らされたその姿は、この災いを司る鬼か何かの妖怪が現れたかと錯覚させるに相応しい風貌であった。
実に彼女は火がどう燃え、どのように焼き尽くすかを厳しく監督するかのようにじっと凝視していた。そこから一歩も動かず、風と煙と炎が混ざり合い、争い、勢いづいて、力の限りを互いに奮う様子を、したり顔で笑みまで漏らして眺めている。その顔と言ったら、この世に並び得るものがないほどの不気味さなのだ。
風が暴れ吹く轟音に紛れたためであろう。寝耳にこの火事を聞きつける者はいなかった。誰ひとりとして出て来て騒ぐことがない間に、火はメラメラと母屋に延焼する。燃え立つ巨大な炎に、叫喚の声が上がった。狂女が嬉々として高笑いをしたのである。

人々が出て来て騒ぎたてるころには、火元の建物の大半は烈火になって、家屋の窓という窓からは炎が噴き出し、もはや手の着けようがない状態に陥っていた。さしもの強風で消防が尽力したにも関わらず、三十数軒をも焼き、午前二時に及んで鎮火に至ったのである。
雑踏の声は怪しい人物が逮捕されたとの報を伝えていた。現場に留まっていたあの狂女が捕まったのだ。
火元だと認定された鰐淵家に燃え残った物は何一つなく、憐れむべき一片の焦土を残しただけであった。家族の消息は直ちに警察が尋問した。使用人は命からがら逃げおおせたけれども、目が覚めたときには既に枕元一面に火が廻っており、仰天して二度三度と家人の名を叫んで避難したので、主人たちがどういう状況になったのかは知らないと言う。
夜が明けても鰐淵夫妻の姿が見えないので、さては逃げ損ねたかと、警察は引き続いて捜索を続けた。
熱灰の下から一体の遺体が、半ば焦げただれた状態で発見された。目も当てられない悲惨の極致だったが、家主の妻であると断定できる面影が焼け残っていた。それならばとその近くを隈なく掻き起こしてみたが、他に新たな発見はなかった。その後、倉庫辺りだと推測される場所から、焦げ崩れた人骨を掘り出した次第である。
酒に酔って逃げ惑ったためか、欲を貪って自身を見失った末か、とにもかくにも夫妻はこの火災で落命したのだ。
家屋も物置も一夜の煙に化してしまって、鰐淵の土地に残ったものは、赤土と灰以外には何もなくなってしまった。風が吹き惑う烈火猛火が紛糾する場所に、唯一もとの形を残していたものは、家主が居間に設置していた金庫だけであった。
別居している直道はあいにく旅行中で未だ帰って来ず、貫一はまさしくちょうどお峯の遺体が発見されたタイミングで、病院から駆けつけた。
彼は三日後には退院する予定だったので、今は傷も癒えて仕事に戻るのに不都合はなかったけれども、事があまりにも不慮で急激で甚大であるゆえに、大きく動揺した。
病後の身をもってこの処理に当たらねばならないのは非常に苦しかったが、全力で万端を処理し、ただただ直道の帰京を待った。
枕も上がらぬ病人だった彼が今や元気に起き上がり、逆に常に病室にやってきては親しげに見舞ってくれた健康で強靭な者が、空しくも燃え残った骨となってしまう。その現実に直面しても弔いの言葉ひとつすら彼の口から出てこなかったのは、貫一にはまだ現実を現実として受け入れることができなかったからだ。
人は皆死ぬ。誰だって知っていることだ。それでもいつも一緒に暮らす人の死は想像しにくいものだ。
貫一はこの五年を過ごした家族が、一人も残さず家屋とともに焼き尽くされて一夜のうちに消えてしまった目に遭ったことで、自分の手持ちの物が理由もなく無くなったかのようにも感じた。こうなった以上、自分の身の上も今後果たしてどうなってしまうのかと、無常さが五臓六腑に沁み渡るのだ。
住む家が跡形もなく焼失したというだけで、見果てぬ夢のような心地になるであろう。まして併せて頼みにしていた夫妻を失ったのだ。ふたりの声と姿が、幻影のように脳裏にこびりついて離れやしない。ほとほと現世と死後の世界の境を彷徨って、あまつさえ久しく続いた無味乾燥の入院生活に飽き飽きしてこの家を思うことが甚だしかったせいで、追慕の情は極めて凝り固まるのである。
せめて何か得るものがあるかもしれない――
夜遅い時間ではあったが、貫一は市ヶ谷から杖の助けを借り、程遠くない焼き跡を弔いに出向くことにした。