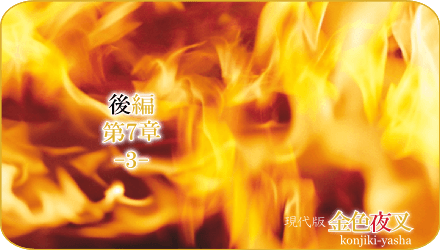嗚咽
嗚咽
ここ数日は風が強く冷え込む日が続いたが、この夜は寒さがにわかに緩んだ。朧月の色も温かみを帯びて、曇るほどでもなくうち霞んだ町筋は静かな眠りに就いている。
燻り臭い悪気は周囲に満ち、踏み荒らされた道は水びたし。燃えがらに埋もれた焼け杭や焼け瓦などが所狭しと積み重なった空き地は、ここが火元だからと板囲いもできず、もはやどこからどこまでが家屋だったのかも判別できないほどに、鰐淵の家は一切の形を焼失してしまっていた。
黒焦げに削れてしまった幹だけが短く残った一列の立木のそばには、うず高く盛り上がった土の山。物置だったのだろう。足を踏み入れると灰燼の熱気が未だ冷めていないことが仄かに感じられる。
貫一は杖をついて、打ちひしがれたまま佇んでいた。彼が立つ位置から二・三歩前方こそ、直行の遺体が発見された場所であった。恨めしい死に顔のような月の光は、肉片が棄てられたかのように一帯に散乱した瓦を照らす。
視界に入る物は全て伏し落ちてしまって、四方の空は物寂しげにがらんどうになっていたので、黒く描かれた自身の影ですら思わず振り返って注視してしまうほどだった。
立ち尽くす貫一の胸には、かつてあった住居の姿がまざまざと去来し、頬を染めるお峯の顔や、苦々しい口元の直行の顔が目に浮かんで、まさに眼前で対峙する心地になっていた。
しばらくは夢想に己を忘れていたが、やがて静かに天を仰ぎ、徐々に肩を落としては、一歩進んでまた一歩戻りつつ、深い物思いに沈む貫一。時折涙をも拭いながら、人生とはなんと物寂しいものなのかと感じ入るのだ。
そもそも親しくした人間たちが、道半ばにして離反しないことはないものだ。それ見たことか、かつては離反によって棄てられた恨みを残し、今回は命を奪われて悲しみに遭い、以前の恨みが未だ消えていないにも拘わらず、また新たな悲しみを添える。
我を棄てた者は去り、棄てない者は死んでしまう。孤独な我だけがただ独り残るのみだ。残ったことを喜ぶべきか、死んだゆえに悼むべきか。残った者は憂い積み重なる中で生き続け、死んだ者は命を絶って倒れる。そもそも生と死の、どちらを憐れんでどちらを悲しむべきなのだろう。
我が煩悶の人生を振り返ってみても、彼らの惨憺たる死と何ら違いはない。ただ異なるのは、この世に留まるか去るかの差だけなのだ。彼らが死なねばならなかったことを、我が人生の苦を慰みとするべきなのか。それとも自身が生き永らえていることで、初めて彼らの死の傷ましさを弔うに足り得ると考えるべきなのか。
我がはらわたは断たれ、心は破れてしまった。彼らの肉は爛れ、骨は砕けてしまった。生きてなお苦しまざるを得ない身ではあるが、それでも魂が消え失せるかと思わせるほどに驚愕させられた彼らの死にざまである。
財産を失い、家を失い、おまけに身体をも失うという、尋常ならざる人生の終焉。極悪重罪な者であっても未だかつてこれほどまでの残虐な辱めを受けたものはおらず、犬畜生に足らない者であってもこれほどの宿命に陥る例はなかろうに。天命か、それとも因果応報なのか。
しかしながら直行が世間に善をもたらさない人物でしかなかったからだと、断じることはできまい。人情は暗中に刃を揮い、渡る世間は至る所に落とし穴を設けるものだ。人は陰に日向に悪事を行うのが常で、一切の悪に手を染めないで済むはずがない。
もしも直行の行いを咎めるべきだったとして、その資格を持つ者が一体どこにいると言うのだろう。貫一にしたって甚だしい悪事を重ねたものの、天に憎まれたわけでもなし、寿命が縮んだわけでもなし、因果応報の宿命もするりと避けてしまったわけだ。彼らの惨死を辱しめてはいけない。自身がたまたま奇禍を免れることができただけなのである。
こう考えた貫一は生前誼を深くしてきた夫婦の死を嘆き、この生き別れを遣る方もなく悲しみ惜しんだ。
そろそろ立ち去るべきかと、家主の遺体が発見された辺りで拝み、また妻の屍が横たわっていた所を拝む。心侘びしく場を離れようとすれば、にわかに胸の内を掻き乱される心地に襲われ、死んでしまった夫婦が弔う者もおらず闇路の奥に打ち棄てられたことを悲しく思うのだ。ああ、もう今しばらく留まろうかと乞いすがる感情に、立ち去るのも忍びなく、再び立ち戻っては積まれた瓦礫の土に佇んでいた。
部屋に戻って亡骸を眼前に限りなく思い乱れるよりかは、ここに居れば亡き人のゆかりの傍ゆえに、遺言にも似た何かの手がかりでも得られるかもしれない。そう思った貫一は、立てた杖に重い頭を載せて、地中に沁み移っているかもしれぬ夫婦の念を瞑想する。しばしの時間が流れ、何か得るものがあったのであろう、貫一の頬をはらはらと涙が伝い零れた。
そこへ夜陰に轟く走行音とともに風のように飛ばして来た車が、焼け場の端に停まった。ひらりと人が降り立った。その人物はすぐに鰐淵の家の跡に歩き進み、やがて歩みを止めた。
焼け瓦を踏みしだく音に気付いた貫一が頭を上げる。人影が近づいて来るのを誰だろうと確認する暇もなく、声をかけられた。
「間さんですか」
「おお、あなたは! お帰りでしたか」
その人は首を長くして待っていた直道だった。忙しなく出迎えた貫一。向かって立つ二人は月明かりに顔を見合っていたが、言葉を継ぐことができず、しばらく何も言い出せない。

「何とも突然のことで、申し上げようもありません」
「はい。この度は留守中のことといい、ご迷惑をおかけしてしまいました」
「私は火災発生時には、まだ病院に居りまして。まさかこんなことになっていたとは全く知らず、夜が明けてからようやく駆けつけた始末です。今更申し上げたところで愚痴にしかなりませんが、私がそばに居られたならば、このような事態にはさせなかったものをと実に残念でなりません。
またお二人にとっても余りにも不意な事故でしたし、それしきのことで狼狽する人でもなかったのに、これが寿命だったのか、全く未練の残ることになりました」
直道は閉じていた瞼をゆっくりと開き、言葉を発する。
「何もかも皆焼けてしまいましたね」
「ただひとつだけ、金庫が助かった以外は全て焼けました」
「金庫がですか。何が入っていたのでしょう」
「現金も少しはありましょうが、帳簿や証書の類が主ですね」
「貸金に関するものですか」
「そうです」
「なんてことだ! それを焼きたかったのに!」
口惜しげな感情がしたたかに顔面に顕れていた。直道の意見が彼の父と相容れなかったために年来別居している内情を、貫一が詳らかに知っておれば、不幸中の幸いで焼け残った金庫の存在が喜びどころか憂いの種となる理由を彼も察知できたであろう。
「家が焼けただの、物置が焼けただのは別段どうってことはないのです。むしろ焼け落ちてしまわねばならないくらいですよ。だからそれは問題ありません。
両親が亡くなったのも、私であれあなたであれ、こうして泣いて悲しむ者はここに居る二人だけ。世間には誰一人――さぞ皆が喜んでいるだろうと思えば、ただただ親を亡くしたことが哀しいというばかりではないのです」
それでも堰を切って流れ出るのが恩愛の涙である。彼を憚っていた父と彼を畏れていた母は、同時に子として彼を慈しむことを忘れてはいなかった。その憚られ畏れられた点を除いては、彼は他の憚られ畏れられていた子よりも多くの愛情を享受していた。
生きてこそ争えた父。亡き今となっては、意見を聞き入れられなかった恨みよりも、孝行できなかった後悔の念が直道の心を責めるのだ。
生暖かい風が急に吹いた。コートの裾が捲れ上がる。このコートは亡き母がくれたものだと、ふと思い出した。なおざりな人生の中で何の徳にもならない程度の施しではあるが、世間に数えきれないほど居る人の中に誰が何の縁もなく物をくれたりしようか。
直道は出張先の測量地から戻って来た身である。この学位と地位を彼に与えても、それを恩としなかったのは一体どこの誰か。恩返しを求める他のアテもなく、恩返しを得ることも叶わなかった父と母は、今や相携えて遥かに遥かに隔てた世界の人になってしまった。
炎々と燃え猛る業火の中で、父と母が苦しみ悶えて助けを呼んだのはどれほどのことか。彼らは果たして誰を呼んだのであろう。思いはここに至って、直道の哀咽は身を震わせ、涙となった。